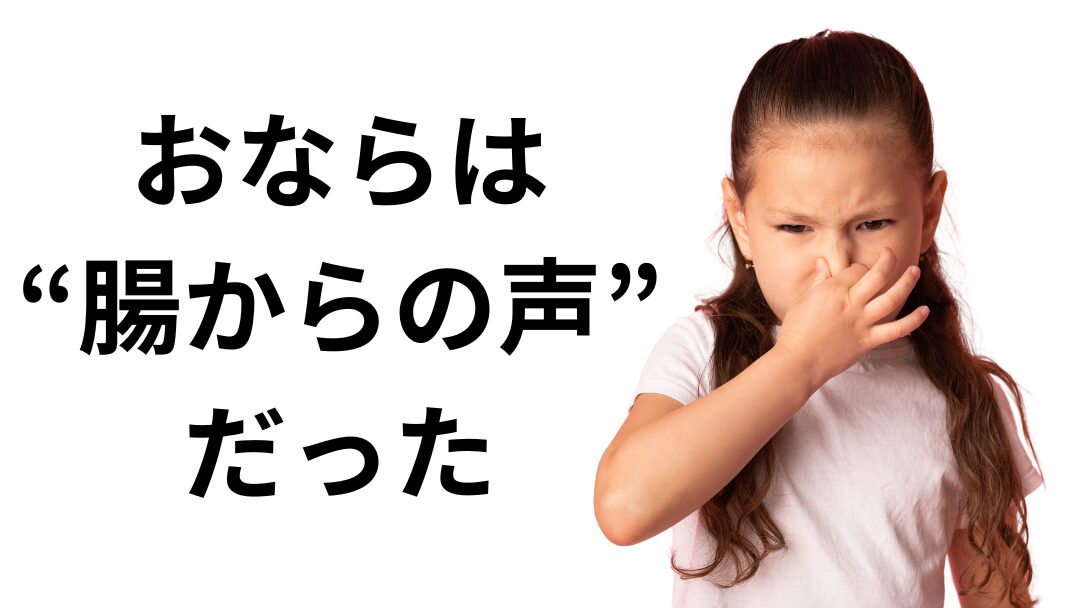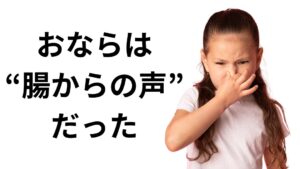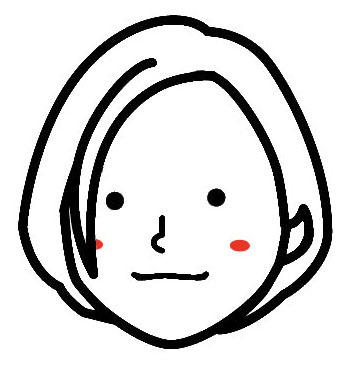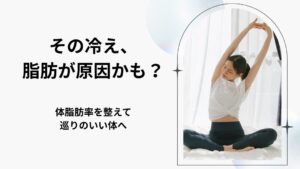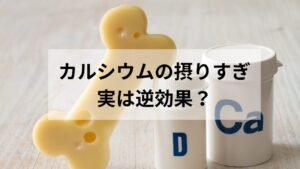「最近、おならが多くて気になる…」「人前で出そうになって、緊張する」「臭いが強くて自分でも気になって仕方ない」――こういったご相談、実は薬局でも伺います。恥ずかしいからこそ相談しづらく、ひとりで悩まれている方も少なくないのだと思われます。
ですが、おならは「恥ずかしいだけの現象」ではなく、実は 腸や消化の働きからのメッセージ であることが多いのです。
今日は「おなら」の仕組み、頻度・臭いの目安、原因、そしてご自宅でできる対策を整理してご紹介します。腸内環境を整えることは、おならだけでなく、全身の健康にもつながりますよ!
1. おならは“正常な生理現象”です
まず強調したいのは、 「おなら」は誰でも出る、自然な生理現象である ということです。腸内で発生したガスが出口(肛門)を通じて排出される、言わば「腸の働き」の一部です。
実際、研究によると、1日におならが出る回数は「およそ8〜14回」あるいは多い人では「20回前後」までを正常範囲とする報告があります。
つまり、数回/日なら心配なし、むしろ腸が働いているサインとも言えます。
ただし、以下のような場合には注意が必要です。
- おならの回数が急激に増えた
- 臭いが強くなった、あるいは臭いの変化を感じる
- 腹痛・下痢・血便・体重減少など他の症状を伴う
このような時は、無理に我慢せずに専門医での相談も検討したほうが良いと思います。
2. なぜおならが出るのか?原因を理解しよう
おならが出るのは、主に次のような仕組みによるものです。
・空気を飲み込んでしまう(“エアスワロー”)
食べる時・飲む時・会話しながら・ガムを噛む・炭酸飲料を飲む…などで、知らず知らずのうちに空気を多く飲み込んでしまうと、腸にガスとして蓄積され、それが排出される原因となります。
・腸内細菌が発酵してガスを作る
腸内に届いた未消化・難消化の食物成分(例:食物繊維、乳糖、発酵性オリゴ糖など)が、腸内細菌によって発酵されるとガス(CO₂・水素・メタンなど)が発生します。これが「おなら」として出てくるわけです。
 CHIKA
CHIKA野菜を沢山食べるとおならの回数が減りそうですが、人によってはお肉より野菜を沢山食べるとおならが出る!という方もおられます。
・食べたもの+腸の働き+習慣の影響
例えば、豆類・キャベツ・ブロッコリー・玉ねぎなどの“ガスが出やすい食材”、また乳製品(乳糖不耐症の方)や糖アルコール(‐olで終わる甘味料)なども原因となりえます。さらに、食べるスピードが速い、よく噛まない、飲み物を一気に飲む、便秘がち、運動不足なども影響します。
・腸の病気・機能異常が背景の場合も
多くは良性ですが、長期的・重度・続く場合には、例えば過敏性腸症候群(IBS)、小腸細菌異常増殖症(SIBO)、消化管の炎症性疾患、乳糖・果糖不耐症、グルテン感受性などの可能性も視野に入れる必要があります。



血糖をコントロールするための一部の薬でも副作用で「放屁」という記述があります。
3. よくある“おならのお悩み”とその背景
● 「おならが多すぎて困る」
頻度が増える原因としては、空気の飲み込み過多(早食い・飲み物を一気飲み・ガム・ストロー)、食物繊維の急増、発酵性の高い食材・糖質、便秘などがあります。腸の中でガスが溜まりやすく、排出機会が増えるためです。
● 「おならが臭い」
臭いの原因としては、腸内細菌が硫黄化合物(硫化水素など)を生成することがあります。特に臭いの強い食材(にんにく・におい玉ねぎ・ビールなど)や腸内環境が乱れている場合に起こりやすいです。
● 「人前でおならが出そうになって緊張してしまう」
これは頻度・臭いだけでなく、「出るかも」という予期不安・ストレスが更に腸の動きを乱すこともあります。腸は「脳―腸相関」の影響を受けるため、緊張・ストレスが空気飲み込みを増やしたり、腸管内のガス移動を遅らせたりする可能性があります。
4. 今日からできる“自然療法”5つ+補足
実は市販薬でも「おならを減らすための薬」というものが売られています。
成分として「ジメチルポリシロキサン」という、貯まったガスをつぶす消泡剤のような働きをする成分や何種類かの整腸菌が配合されていたりします。(例:ガスピタン)
ここではまず「薬に頼る前にまずできること」を整理してみたいと思います。
1. 食物繊維の摂取バランスを見直す
食物繊維は腸内環境改善に非常に大切ですが、「不溶性繊維だけを急激に増やすと」ガスが溜まりやすくなる可能性があります。腸がまだ慣れていない状態で急に量を増やすと、腸内細菌の発酵が活発になりすぎてしまうためです。
そこで、水溶性+不溶性のバランスを意識しながら、少しずつ増やすことをお勧めします。例えば、バナナ・オートミールなど水溶性繊維を含むものも併せて摂るといいですね。
2. プロバイオティクス・腸内善玉菌を意識する
ヨーグルトや発酵食品など「善玉菌を増やす」取り組みは、腸内細菌叢のバランスを整え、ガス・膨満の軽減に役立つという報告もあります。
例えば、特定の菌株ではおならの回数や不快な膨満感が改善したという結果もあります。
ただし、「全てのプロバイオティクスが必ずガスを減らす」という確固たる証拠はまだなく、「こういう可能性があります」と段階としてお伝えしておきます。
3. 食後にハーブティーを飲んでみる
ペパーミント、フェンネル(ウイキョウ)、ジンジャーなどは、「消化を促進し、胃腸のガスを軽くする」補助的役割があるとされます。例えばジンジャーの摂取がガス・膨満の軽減に関連するという報告も。
食後に1杯、気持ちを落ち着けながらゆっくり飲むのも、腸のSOSを和らげるひとつの手段です。
4. 食事のペース・よく噛む・空気を飲み込まない習慣
「一口30回を目安に噛む」「早食いや会話しながら大量に飲み込むのを避ける」「炭酸飲料・ガム・ストローを控える」など、腸に余分な空気を入れない工夫が非常に有効です。
食事をする時は、テレビを見ながら・スマホを見ながらではなく、「味わって」「噛む」ことを意識しましょう。腸が「食べものよし」と判断して消化にスイッチを入れやすくなります。



実は私もかなりの早食いで、気を付けないと・・と思っています
5. 発酵性糖質(FODMAP)を意識して一時制限+再導入
特に「おなら・膨満感・IBS(過敏性腸症候群)」が気になる方には、発酵性のオリゴ糖・二糖・単糖・ポリオール(FODMAP)を含む食品に注意が必要です。玉ねぎ、にんにく、小麦製品、乳製品、特定の果物などが代表例です。



私も、今まで食べてビックリするほどオナラが止まらなくなった食べ物が二つあります!
・とあるコンビニで買った煮卵(他のコンビニのものや自分で作ったものは大丈夫でした)
・デーツで作られたシロップ
特にデーツシロップはビックリしましたね!砂糖を使うより、なんとなく良さそう・・と思って使ってみたのですが。。
※もちろん、個人差もあると思いますし製品によっても異なると思います。
たとえば2週間程度これらを控えてみて症状が落ち着いたら、ひとつずつ戻して「自分にとって反応が出る食品」を探すという方法が推奨されています。もちろん、制限しすぎて栄養バランスを崩さないことが大前提です。
5. さらに押さえたい補足ポイント
便秘・運動不足・水分不足はガスを助長します
便秘になると、腸内に滞留する食物残渣が長く発酵され、ガス・臭いが増える傾向があります。Mayo Clinic また、運動不足・水分不足も腸の動きを鈍くし、ガスの排出が滞りがちです。まずは「便通を整える」「1日1.5〜2L程度の水分」「毎日少し歩く」なども併せて考えましょう。
「臭いや色、急激な変化」は要注意
おならそのものに“色”はありませんが、便の色や臭いの急激な変化、また血便・ひどい腹痛・体重減少などを伴う場合は、より重い消化器疾患の可能性もあるので即病院へ。
薬やサプリ、整腸剤も場合によっては検討
整腸薬も、さまざまな種類がありますね。ご自身に合ったものを見つけることができればGoodです。
6. まとめ
「おならが出る」「臭いが気になる」「人前で出そうで不安…」――これらは“恥ずかしい”からと言って放っておいていい話ではありません。むしろ、腸からの“ちいさな声”として、「少し立ち止まって見直すチャンス」と捉えてほしいのです。
腸は「第二の脳」とも呼ばれ、消化・栄養・代謝・免疫・さらには気分とも深く関わっています。ですから「おならが改善する=腸環境が整ってきている」=身体全体の健康にもプラス、という流れを目指しましょう。
腸の声を、どうぞ味方につけて。今日からできる小さな習慣が、明日の快適なお腹と自信につながります!