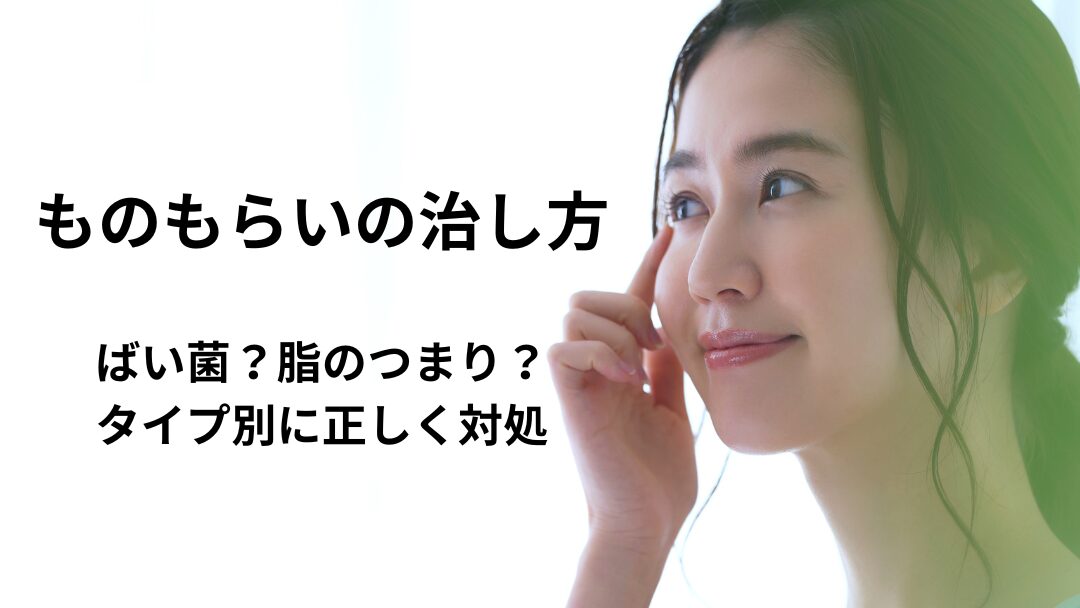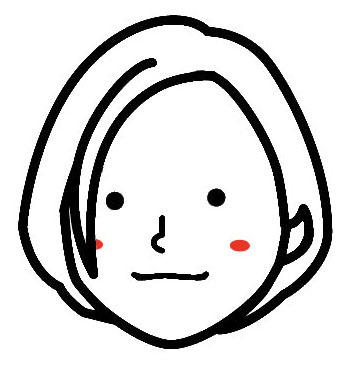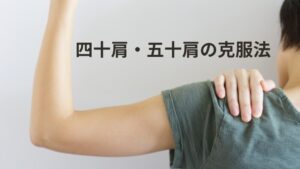先日行った美容院での会話。
担当の美容師さんがふと、こんな話をしてくれました。
 美容師さん
美容師さんこの間、目にものもらいができちゃって。けっこう大きくなって目立つから、さすがに病院に行ったんですよ。
1件目の眼科では目薬を出されたんですけど、全然よくならなくて…。
それで2件目の眼科に行ったら『目を温めること』と『マッサージ』をすすめられたんです。
それをやったら、目の中のゴロゴロが“プチッ”って潰れて、それで治ったんですよ!
とのこと。
この話を聞いて、私はすぐに「それは“霰粒腫(さんりゅうしゅ)”だったのでは」と思いました。
「ものもらい」とひとことで言っても、実は2つのタイプがあるのです。
「ものもらい」の種類と原因
| タイプ | 原因 | 特徴 |
|---|---|---|
| 麦粒腫(ばくりゅうしゅ) | ばい菌 | 赤くて痛い、うみが出る |
| 霰粒腫(さんりゅうしゅ) | あぶらがつまる | コロコロふくらむ、痛くないこともある |
美容師さんの場合は、あぶらがつまってできる「霰粒腫」だったのでしょう。1件目の眼科では、おそらく抗菌剤の点眼薬が処方されたのだと思いますが、ばい菌が原因ではない霰粒腫には効果が薄かったと考えられます。
霰粒腫は、まぶたにある「マイボーム腺(脂を出す管)」がつまって、脂がたまり、しこりのようになってしまう症状です。そこで効果的なのが、「温めること」と「マッサージ」!
麦粒腫(ばくりゅうしゅ)と霰粒腫(さんりゅうしゅ)に使われるお薬(処方薬)
| 種類 | 使用される薬 | 主な製品名(例) | 使用される場面 |
|---|---|---|---|
| 抗菌点眼薬 | レボフロキサシン オフロキサシン ガチフロキサシン | クラビット点眼液 タリビッド点眼液 ガチフロ点眼液 | 麦粒腫:〇(基本治療) 霰粒腫:△(感染を伴う場合のみ) |
| 抗菌眼軟膏 | オフロキサシン | タリビット眼軟膏 | 麦粒腫でうみが出ているときなどに使用 |
| ステロイド点眼薬 | フルオロメトロン | フルメトロン点眼液など | 霰粒腫:△(炎症が強い時・感染なしに限る) ※慎重な判断が必要 |
| 抗菌薬(内服) | セファレキシン アモキシシリン クラリスロマイシン | ケフレックス サワシリン/パセトシン クラリス | 麦粒腫:〇(腫れが強い、広がっている場合) 霰粒腫:△(膿がある、再発時) |
ものもらいになり眼科に行ったとき、上の表にあるようなお薬を処方してもらったことがあるのではないでしょうか。
これらの成分を含むお薬は市販薬にはないので、眼科に行って処方してもらう必要があります。



この中でステロイドに関してはなぜ「慎重な判断が必要」とあるか・・?
これは眼圧が上がってしまうことがあるからなんです。
目を温める意味とは?
目を温めるというと、「疲れ目に効く」「血行をよくする」というイメージがあるかもしれません。でも実は、目の中の脂(あぶら)を溶かして流しやすくするという大切な目的もあります。
このように温めて治療する方法は「温罨法(おんあんぽう)」と呼ばれています。特別な道具は必要ありません。たとえば、蒸しタオルを使えば、家庭でもすぐに実践できますね。
マイボーム腺マッサージの基本的なやり方
- 手をきれいに洗う
- 温かい蒸しタオルで5〜10分、まぶたを温める
- 上まぶたは上から下へ、下まぶたは下から上へやさしくマッサージ
このマッサージを習慣づけることで、マイボーム腺がつまりにくくなり、霰粒腫の予防にもつながります。
治らないときはセカンドオピニオンも◎
今回の美容師さんのように、1件目の治療が合わなかった場合、別の病院で改めて診てもらうことはとても大切です。ドクターの見立てによって、処方内容が変わることはよくあるからです。
ただし、霰粒腫が大きくなりすぎてしまった場合は、温めたりマッサージしたりしても改善が難しく、切開手術が必要になることもあります。放っておかずに、早めに受診するのがおすすめです。
「目から健康がわかる」ドクターも
少し話はそれますが、眼科の先生の中には「目を見ただけで体の不調を言い当てる」ような、まるで名医のような方がいらっしゃいます。
たとえば、私の友人は眼科で「ちょっと血圧が高いかもしれませんね。測ったことありますか?」と聞かれ、実際に測ってみたら上が160を超えていたそうです。また、別の方は「何か心配事を抱えていませんか?」と見抜かれてドキッとした、なんて話もありました。
「余計なお世話だ」と感じる方も中にはいて薬局で怒り出す方もいますが、こうした経験豊富なドクターの観察力に驚かされることが本当に多いです。
予防こそが最大の治療
美容師さんが最後に



その先生ね、目を温めたりマッサージするのは予防にもいいって教えてくれたんですよ。すごく良心的じゃないですか?
と話してくれました。
症状が出てから対処するのではなく、日頃から目をケアすることが大切なのだということを改めて感じました。
ちょっとした違和感を放っておかず、日ごろから自分の体の声を聴くことやセルフケアを心がけたいですね。